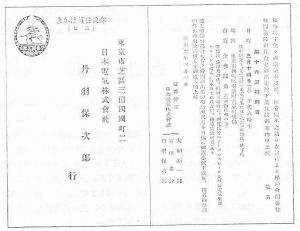【20号】車両の磁気浮上の研究/山村昌
我が国では鉄道は交通量(man-km)の半分以上を運んでいて、依然として最も重要な交通手段であるが、いろいろな問題に直面している。技術的な面では騒音と保守の問題がある速度を増すと、加速度的に騒音と保守量も増加するので、これによって実用の速度が制限されている面が多い。これらの問題に眼をつぶるとしても、300 km/h以上の速度を考えると、車輪とレールの間の粘着係数が不足して、充分な推力とブレーキ力とを得ることができないし、安全性も低下してくる。これらの問題を解決する未来の軌道車として、非接触形の支持案内を行う車両の開発が先進諸国で行われている。非接触形に空気浮上と磁気浮上とがあって、前者の方がフランスやイギリスなどで早くから開発が進められたが、現在では磁気浮上の方が有利であることが定説となっている。
磁気浮上のことをmagnetic levitationという。Oxford辞典を引くと、levitationとは「神霊現象の力によって物体を空中に持ち上げること」となっている。車も翼も無くて、見えない力によって浮上する車両には、ぴったりした名称である。磁気浮上に起電導マグネットを用いる反発形と、常電導マグネットの吸引力による吸引形とがある。この他、 リニアモータで推進力と支持案内力とを同時に発生する方式など、いくつかの方式が提案されているが、世界的に見ても上記の反発形と吸引形とに、開発の努力が集中している。
超電導反発形では車の床下に設置された超電導マグネットの作る強い磁界(地表面で0.5Tesla=5,000ガウス程度)が走行して、地上に設置されたアルミ板または閉コイルの二次回路に発生する誘導電流と、磁界との間の反発力によって、車体を浮上させるもので、浮上高を大きく(10~20cm)取れる特長があるが、飛行機のように、地上を滑走してからでないと、浮上しないこと、浮上中の安定性(ダンピング係数)が小さいこと、超電導マグネットを液体ヘリウムで極低温に保たねばならないこと、強い磁界が車室の内外に広がること、抗力が発生して、特に加速中の抗力が非常に大きくて、加速に困難があること、などの問題がある。
常電導吸引形では、地上側に地面より高い位置に水平に固定された鉄レールに、車上の電磁石が対向して、両者の間の吸引力で車体を支持案内する。両者の間のギャップ長を一定に保つためには、電磁石の電流を閉ルーブ制御する必要があるので、制御回路の信頼性が高い必要があるが、速度が零でも浮上できる特長がある。浮上のための消費電力は、ギャップ長が15mm程度で2~4kW/tであって、推進の電力に比べて、小さい。高速を出すためには、地上レールの工作精度を高くしなければならない。
我が国では国鉄が5年前に、東京‐大阪間に起電導反発形の磁気浮上車によって第2新幹線を建設して、500 km/hで所要時間1時間のサービスを10年後に行うという計画を発表した時期に、これに刺戟されて、私の研究室では常電導マグネットによる磁気浮上の可能性の研究を開発した。1972年にドイツで常電導吸引形磁気浮上のテストに成功したとのニュースが入ったとき、先を越されて残念に思ったが、我々の考えが正しかったことに気を強くした次第でもある。その後の研究は順調に進んで、1点支持、ついで2点支持の浮上テストに成功し、一昨年1月には2m×1.2m、350kgのテスト車の浮上テストに成功した。これは室内実験ではあるが、 リニアモータも備えており、我が国においては最初に成功した磁気浮上のテストとして、記録されるべきであると考えている。
それまで起電導反発形に一辺倒であった我が国の業界も常電導吸引形に関心を持つようになり、一昨年日本鉄道技術協会内に低公害列車開発委員会が発足し、運輸省にも低公害列車総合委員会が設置されて(私が両方の委員会の委員長)、常電導吸引形磁気浮上車の開発に着手した。2年を経ないうちに2.8m×1.7m、2tの試験車と180mの試験線とを完成して、テストを開始したことを、昨年末に発表することができた。なお同様なテストの発表が他の団体からもあったが、上述したところの当研究室の成果から考えて、取り立てて大騒ぎをするには当たらない。むしろ今後の実用車を目指して研究開発の成果を挙げることが大切であると考えている。
当研究室の仕事は、助手諸君のほか、大学院生、卒論の学生諸君の努力によって支えられている。磁気浮上車はリニアモータによって非接触推進されるのであるが、 リニア誘導電動機の研究もここ10年余り続けていて、磁気浮上と併せて50編余の論文、報告、著書を発表することができた。なかにはリニア誘導接の端効果理論、浮上用マグネットの速度特性の解析など、常電導磁気浮上方式の理論的な基礎を与えたものもあって、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、イタリーの学会や大学から招待論文や講演をたのまれて、国際文化交流にもいささか役立っていると考える。
世界的に見ても、また我が国でも、常電導吸引形の方が理論的にも実験的にも進んだ段階にあって、低速から300km/h以上の超高速域までの広い速度範囲で、従来の鉄道のかかえる間題をすべて解決する新しい形の交通システムを生む可能性が大きい。エネルギー政策上から見ても、電力に変わるエネルギーならなんでも利用でき、エネルギー効率のよい未来の大量交通手段である点も、見落としてはならない点である。実用化までには技術的にも問題が残されているが、開発資金面での、またさらには交通政策上での困難が少なくない 同窓生各位の御支援をお願いする次第である。
(昭和16年卒 東大教授)
<20号 昭51(1976)>